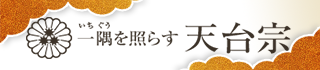今月の言葉
さとり
病(やまい)のないのは第一の利(り)、
足(た)るを知るのは第一の富(とみ)、
信頼あるのは第一の親しみ、
さとりは第一の楽しみである。
これまでの言葉
長福寺について
開門時間
9:00~18:00
通年
- 年中無休
- TEL:029-269-2906
- FAX:029-269-5977
交通・アクセス
公共交通機関でお越しの方へ
- 常磐線 水戸駅にて臨海大洗鹿島線乗換
- 常澄駅(水戸駅より2駅10分)下車 徒歩25分(2km)
お車でお越しの方へ
- 常磐自動車道・水戸JCより東水戸道路に入り、水戸大洗IC出口より約3分
- カーナビを利用すると山門階段下の正面駐車場に案内されますが、階段が急ですので、大串貝塚ふれあい公園前の門を奥に進み、客殿前駐車場をご利用ください。